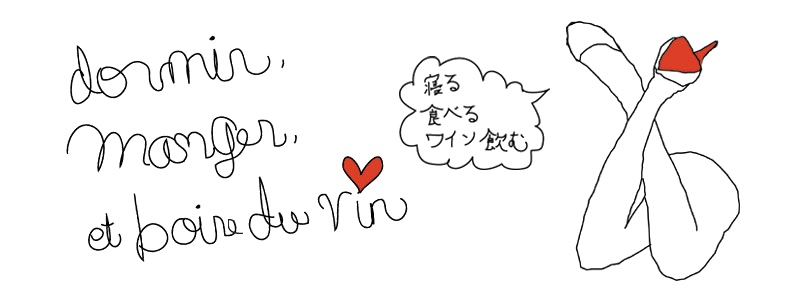二人の姿がなくなり、空間を舞っていた細かな動きの分子がゆっくりと綿埃のように底に落ち着く。場は静寂を取り戻す。そしてセロの音がその静寂に静かに切れ目を入れ、ゆっくりと時空が歪む。戯曲の幕開け。
その夜、レオナルド・ダ・ヴィンチが現れると聞きつけ、わたしと恋人はその場所にはぜひ立ち会わなければと、会場に出向いた。日本海の風が一日中吹き付け、春分の日なんてそんなこと言うから少し春の陽気を期待してしまうじゃないか、本当に温かくなんてなるのだろうかと気持ちが頑なになりそうな、「もう寒いの飽きた」なんてごちる、そんな気温の低い日が続いた週の週末、金曜日の夜。
特別な用でもない限り、こんな寒い日に大濠公園に来ることないよねなんて言いながら、駐車場に車を停めて、コートのボタンを上まできっちり留めて、マフラーをぐるぐる巻きにして歩き出す。いつもの入り口から歩き出すと、黒く光る池と、等間隔でジョギングコースに立つオレンジ色の灯りがとても綺麗で、思ったよりも冬の夜の公園を散歩する人が多いことに驚きながら、寒さも気にならなくなりふたりで高揚した気分を楽しみながら会場へ向かった。
その夜の会場は公園の中にある能楽堂。もちろんいつもは能が演じられる場所。能楽堂に入るのは初めてだった。わたしたちにはめずらしく遅刻せず、というか開場時間の10分前くらいには到着した(!)にもかかわらず、すでに長い列が作られていた。久しぶりに会うイタリア会館の館長ファミリーに挨拶をし、列に並ぶ。来ている人たちの年齢層は少し高めで皆落ち着いていたが、今夜何が起こるのだろうかという少し子供のようにはしゃぎたいような雰囲気を皆隠せずにいるのが感じとれた。白檀の香りが鼻先をかすめる。
空気の中にセロの音色が吸い込まれ、会場は再び静寂に包まれた。ゆっくりと幕口から、少し猫背の年老いた男が静かに橋掛けリを歩いてくる。黒いベレー帽に青白い顔、銀色に光る豊かな長い髭、白いブラウスの上に纏う黒いスモック、細い二本の足、そして白足袋。ゆっくりとレオナルド・ダ・ヴィンチとの対話が始まる。
絵画と詩について、絵画と音楽、彫刻、科学との関わり、彼が何に基づいて表現をしているか、彼の分析のもととなるものは、水について、愛とは何か、魂とは...etc
ゆっくりと紡ぎだされる彼のイタリア語は時間と空間を超えてわたしたちの耳に届く。
「白貂を抱く貴婦人」のこと、「ウィトルィウス的人体図」 のこと、「最後の晩餐」に描かれた十二使徒の動きのこと、
そして― 「モナリザ」のモデルとは一体誰なのか。
彼は背を向け立ち去る。一瞬立ち止まり振り返ったときの彼の眼差しは、空間にぎっしりと配列されたすべての言葉を集約し、問いへの答えを語った。その彼の 後ろ姿と眼差しの光は、ひっそりと光を放つ小さな石のように確固たる重さと存在感を持ってわたしの内にかたちを残した。そして彼は姿を消した。
最近”表現すること”についてずっと考えていた。対象やその方法、衝動や欲望。―その行為と引き換えにわたしは乞食になれるか―
その一連のことにつながりそうなものが、その夜にはあった。
時間の境目にそびえ立つその壁画。朝早くやってきて、彼は壁の前に立つ。何時間も立ったまま。そしてひと塗りを足す。そして壁の前からゆっくり立ち去る。その一連の光景を観察する。わたしの眼にレオナルド・ダ・ヴィンのその後ろ姿の残像がありありと映しだされる。
あの夜からあの光る石がわたしの手の中に在る。
ESSERE LEONARDO DA VINCI われ、レオナルド 福岡公演
白足袋のレオナルド・ダヴィンチへ