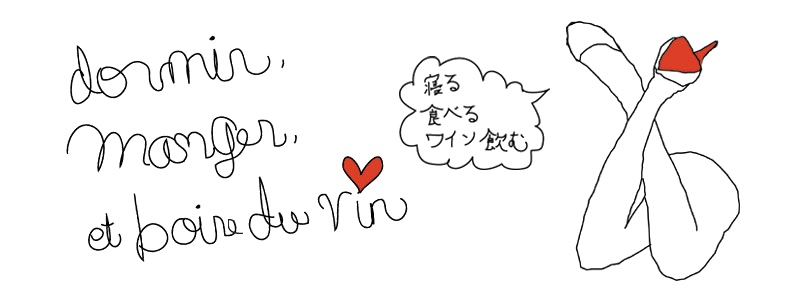そもそも人の味覚の趣味って何きっかけで、いつ形成されるのだろうか?
祖母のきんぴらごぼうとか、筑前煮とか今でも大好物で、いたって普通の日本家庭料理で育ってきている。今でも和の味は大好きで、納豆と、祖母の作った塩昆布で米を食べている。
だけど、何か適当に自分だけの晩御飯とか、好きに作る料理なると、その時食べたいものを炒めたり蒸したりして、例えばクミンと塩・胡椒で味付けをする。クミンさえあれば万事OK!と言っても過言ではない。
だけど、何か適当に自分だけの晩御飯とか、好きに作る料理なると、その時食べたいものを炒めたり蒸したりして、例えばクミンと塩・胡椒で味付けをする。クミンさえあれば万事OK!と言っても過言ではない。
で、例えば、まだあんまり仲良くないくらいの人と普段作る料理の話とかになって、よく、「えー、オレガノ?ローズマリー?お洒落ー!」とか言われて、心の中で、あー、お洒落とか、そういう領域の話じゃないんだな~、あらま、ちょっぴりめんどうくさいわ、オムライスしか作らないって言っときゃよかった的な感じになる。わたしの中ではオレガノもわさびも同じくらい、もう本当に普通の、そして必要な味覚なのだ。
好きになった強烈的なきっかけとかも、おそらくない。ただただ自分にとっては自然な味覚で、もともと塩辛いのが極端に苦手なので、どちらかというと醤油とかがちょっと苦手だったりする。モチモチした食感が苦手なので、お餅も、白米もあんまり好きじゃない。
で、そんなんだから、過去の彼氏たちに料理なんか作る時、せっせこそういうスパイスだのハーブだのを使った料理を作ってたんだけど、あんまり喜ばれた記憶がなかった。日本人男子は和食が好きなのだ。(当たり前か。)それで、和食が食べたいといわれるので、それじゃあ作りましょかって作ってきたんだけど、途中で気づいたのだ。和食、食べるのは大好きだけど、自分で作るのはそんなに好きじゃないってことに(笑)。和食特有の絶妙な味加減のむずかしさとか慣れの問題ももちろんあるんだけど、なぜか自分の中でしっくりこない何かがあったのだ。
好きになった強烈的なきっかけとかも、おそらくない。ただただ自分にとっては自然な味覚で、もともと塩辛いのが極端に苦手なので、どちらかというと醤油とかがちょっと苦手だったりする。モチモチした食感が苦手なので、お餅も、白米もあんまり好きじゃない。
で、そんなんだから、過去の彼氏たちに料理なんか作る時、せっせこそういうスパイスだのハーブだのを使った料理を作ってたんだけど、あんまり喜ばれた記憶がなかった。日本人男子は和食が好きなのだ。(当たり前か。)それで、和食が食べたいといわれるので、それじゃあ作りましょかって作ってきたんだけど、途中で気づいたのだ。和食、食べるのは大好きだけど、自分で作るのはそんなに好きじゃないってことに(笑)。和食特有の絶妙な味加減のむずかしさとか慣れの問題ももちろんあるんだけど、なぜか自分の中でしっくりこない何かがあったのだ。
で、うすうす感づいていたものの、20代後半くらいで、遅ればせながら気づいた。
”もしかしたら、わたし...味覚の趣味が変わってるのかもしれない”
...
恋人はフランス人なので、もともとがハーブとかスパイスの味覚の国で育っている人。だからわたしの味覚を「変」だとはとらえずにいてくれている。そうなると、料理をするのが楽しいのだ。
わたしの親友は、何故かカレーが大好きで、彼女がひとり暮らしの頃はほぼカレーしか作っていなかった。スパイスからカレーを作ることが本気すぎて、そして彼女の作るカレーが美味しすぎて、カレー屋をしろと色んな人から言われている。彼女の作るダルのカレーとか、辛くて美味しすぎてもう、食べた人みんな虜になっている。本当に彼女が店をしたら流行るんじゃないかと思う。
うまいことできている。変なやつにはそれに合った人に出会うのだ(笑)。
結局のところ、食べるものが自分の心と体を作っている、と思うので、「食べること」は大事にしたいし、一緒にいる人とは「味わうこと」を大切にしたいと思う。
最近「食べること」に対していろいろまた考え始めている。何を食べるのか?何を食べないのか?当たり前のように目の前に差し出されるものは、果たして自分にとって本当に必要なものなのか?それとも本当は必要でないのではないか?本当に好きなのか?それとも、好きだと思っているだけなのではないか?
食べ物に限ったことでない。疑問を持って自分で答えを探すことが必要だと思う。ストイックになり過ぎる必要はないと思うけれど、麻痺されて思考がぶよぶよになったまんまはよくない。本当の意味で”気持ちのいいこと”を自分で探すことが大事だと思う。